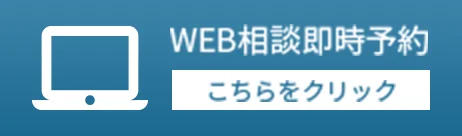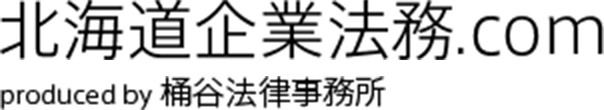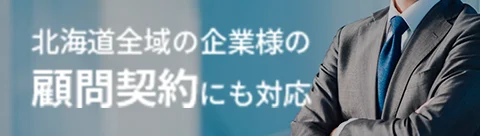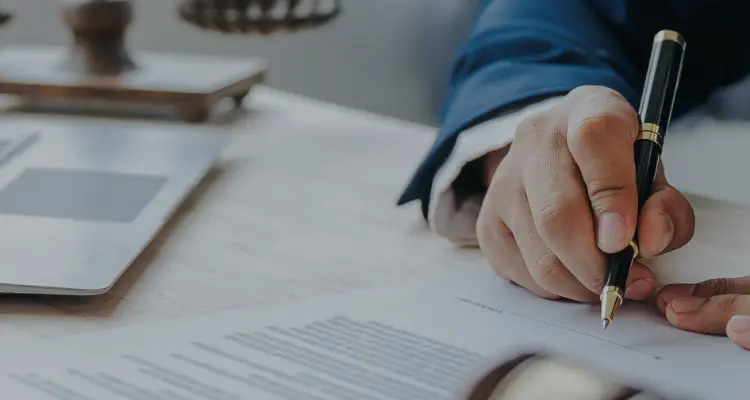- 企業法務一般、顧問契約
ウェブからの予約客の無断キャンセルに対応するための利用規約の整備
Q
弊社は飲食店を経営しており,弊社ホームページ上に利用規約を掲載した上でネットから予約できるようにしてあります。最近,ホームページから予約があった団体客の無断キャンセルがあり,売上も立たず仕込んだ食材も無駄になって大変な目に遭いました。これまで利用規約にはキャンセル時の定めがなかったのですが,今後同じようなトラブルが起こらないようにするために,新しくキャンセル料の規定を設けてもいいものでしょうか。利用規約を変更する上で,法的に気をつけなければならない点があれば,教えてください。
A
いわゆる予約のドタキャンに伴うお店の被害については,法律的には損害賠償請求が可能な余地があるものの,弁護士に依頼したり訴訟をしたりまでして回収するのは費用対効果が低く,現実的には難しい場合も多いと思われます。
そのため,できるだけドタキャンが起きないようにホームページや利用規約を整備しておくことが非常に重要であり,利用規約においてキャンセル料を明確に定めておくことには大きな意味があります。あらかじめ利用規約にキャンセル料をはっきり書いておけば,それだけでドタキャンに対する抑止力になります。ただキャンセル料を定めるだけでなく,予約時に氏名・住所・連絡先といった予約者の個人情報を必ず入力させるようにして,さらに多人数での団体予約の場合には電話での予約確認を必須にする等,ドタキャンを未然に防ぐための仕組みを徹底することが望ましいと思います。
また,実際にドタキャンが生じて損害が生じてしまった場合にも,利用規約の定めというわかりやすい根拠をもってキャンセル料を請求することができますので,弁護士に依頼したり訴訟を起こしたりまではせずにトラブルを解決することができる可能性も高まります。
利用規約にキャンセル料の定めを置く場合には,顧客がその内容を理解・納得して予約をしたということが明確になるように,予約フォームに「利用規約に同意する」というチェック項目を設けることが望ましいと思います。
御社の場合は,ホームページに既に掲載されている利用規約を改正して新しくキャンセル料の規定を設けることになりますが,そのような改正をすること自体には法的な問題はありません。利用規約を改正した後に予約をした顧客との関係では,改正後の規約に基づいてキャンセル料の支払を求めることができます。他方,利用規約を改正する前に予約を受け付けた顧客については,実際の来店日までに利用規約が改正されていたとしても,改正前の利用規約に基づいて対応することが無難でしょう。
ただし,御社と顧客との間の予約取引については基本的に消費者契約法の適用があり,平均的な損害の額を超えるような高額のキャンセル料の定めをすると無効となってしまうおそれがあります(消費者契約法9条1項1号)。キャンセルの時期によって段階的に金額を設定するなどして,キャンセル料が高額になり過ぎないように留意しましょう。
また,御社のホームページ上の利用規約については,ホームページを通じて予約をする顧客に対して一律に適用する趣旨のものですので,いわゆる「定型約款」として民法上の定型約款に関する規定の適用を受ける可能性があります。定型約款の定めの効力については,信義則に反して相手方の利益を一方的に害するような定めを無効とする規制がありますので(民法548条の2第2項),この規制との関係でも,やはりキャンセル料が高額になりすぎないよう留意する必要があります。
【Web相談即時予約】について
当事務所があらかじめ設定したご予約カレンダーの日時と、ご相談者様(企業のお客様に限ります)のご都合が合う場合には、お申し込みと同時に当該日時での Web 相談予約を完了していただけます。
紛争やトラブルのご相談だけでなく、法務に関する一般的なご質問への対応も可能ですので、ぜひお気軽にご予約ください。
※ご予約カレンダーに表示されない日時にWeb相談をご希望の場合は、
お問合せフォームからお申し込みください。